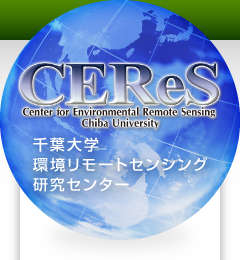教育
国立大学法人の環境リモートセンシング分野における共同利用・共同研究拠点となる研究センターとして、学部・大学院教育と密接に連携しながら後継者の育成を行っております。
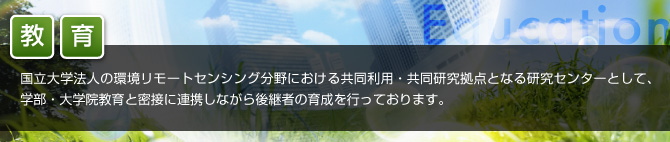
教務に関するお知らせ、開講通知、受講の案内等
CEReSは国立大学法人の環境リモートセンシング分野における共同利用・共同研究拠点となる研究センターです。直接対応する学部はありませんが、教員は大学院において専門教育を行い、また、学部においてもその一部を担っています。
平成29年4月より、理学研究科、工学研究科及び融合科学研究科に分かれていた理工系大学院教育組織は統合され「融合理工学府」が新設されました。大学院では、この「融合理工学府」の中に新しい専攻として「地球環境科学専攻」が設けられ、その中に、CEReSの教員全員が参加する新しい「リモートセンシングコース」が誕生しました。
詳細は、融合理工学府HPをご覧ください。
これにともない、CEReS教員は大学院工学研究院の所属となり、学部兼務は次のようになります。
〇 理学部: 地球科学科
〇 工学部: 総合工学科 (都市環境システムコース、情報工学コース)
(情報画像学科の在校生については、引き続き授業を担当予定です。)
これらの学部・コースでは、リモートセンシングに関する授業を履修できる予定です。
CEReSでは、これまで20年以上にわたる環境リモートセンシング分野における研究・教育を踏まえ、これからの時代のリモートセンシングを担う人材育成を行って参ります。
CEReS教員による開講科目(2019年度)
2016年度からターム制となりました。
T1:第1ターム(4〜5月)、T2:第2ターム(6~7月)、T3:第3ターム(8~9月)
T4:第4ターム(10〜11月)、T5:第5ターム(12~1月)、T6:第6ターム(2~3月)
と読み替えてください。
普遍教育(いわゆる教養課程に相当します)
- 教養コア科目 「宇宙からの地球表層観測」(市井)T2火4
- 教養展開科目 「地球環境とリモートセンシングA」(CEReS教員)T1木2
- 教養展開科目 「地球環境とリモートセンシングB」(CEReS教員)T2木2
- 専門基礎科目 「力学基礎1(3)」(本多)T1-2水2
学部の講義(各学部で専門教育の一部を担当しています)
- 理学部 専門科目(地球科学科) 「環境リモートセンシング概論-1」(近藤・本郷)T1月曜2限
- 理学部 専門科目(地球科学科) 「環境リモートセンシング概論-2」(樋口・入江)T2月2
- 理学部 専門科目(地球科学科) 「大気リモートセンシング-1」(樋口)T1金2
- 理学部 専門科目(地球科学科) 「大気リモートセンシング-2」(入江・齋藤)T2金2
- 理学部 専門科目(地球科学科) 「地球科学英語」(樋口)T4-5木1:学科教員で分担、1コマ担当
- 理学部 専門科目(地球科学科) 「地球科学基礎セミナー」(齋藤)T1-2木1:学科教員で分担、1コマ担当
- 理学部 専門科目(地球科学科) 「リモートセンシング入門」(近藤)T4-5他
- 理学部 専門科目(地球科学科) 「リモートセンシング・GIS実習」(本郷)T1-2他
- 工学部 専門科目(総合工学科) 「リモートセンシング工学」(本多・梶原)T4-5金2
- 工学部 専門科目(総合工学科) 「環境リモートセンシング」(市井・久世)T1-2火2
- 工学部 専門科目(総合工学科) 「リモートセンサ環境計測」(ヨサファット・久世)T4-5金4
- 国際教養学部 専門科目(国際教養学科) 「気象情報論」(樋口)T1月3
大学院融合理工学府地球環境科学専攻
博士前期課程・博士後期課程 専門科目(共通)
- 地球環境科学専攻特別講義Ⅱ(久世・近藤・ヨサファット・樋口)T1-2金2
- 地球表層観測学(近藤・本郷・樋口)T1-2月3
- 地球環境計測学(入江・梶原・楊)T4-5水3
博士前期課程・博士後期課程 専門科目(リモートセンシングコース)
- 放射理論基礎(久世・齋藤・ヨサファット・椎名)T1-2木3
- 大気リモートセンシング(入江・齋藤)T4-5火2
- 陸域植生リモートセンシング(本多・梶原)T1-2木4
- 水循環リモートセンシング(樋口・石坂)T3集中
研究会・ゼミ
CEReSセミナー CEReSで学ぶ学生たちの交流と、研究発表
研究室のゼミ案内
- 久世・齋藤研究室 --- 火曜日3時限:論文講読、金曜日3時限:研究紹介
- 近藤研究室 --- 月曜日5時限(学部・研究生ゼミ) :水曜日5時限(大学院ゼミ)総合棟8階第2会議室
- 樋口研究室--- 木曜日2時限
大学院GP「地球診断学」創成プログラム --- 終了しました
「魅力ある大学院教育イニシアティブ」 --- 地球診断学創成プログラム-を2006年度から実施しています。このプログラムでは、地球全体から地域スケールまでの地球表層構造の知見を統合し、マクロな構造から遺伝子レベルに至る自然の階層構造を把握することによって、その変化の兆しを発見し、現場における問題の本質を理解するために、現場における検証とモデルによる予測を行う能力形成を醸成することを目的とする大学院教育を行います。地球科学・生態学・情報科学の融合により、独創性豊かな人材の育成を図ります。
リモートセンシングに関する教科書
- 「基礎からわかるリモートセンシング」日本リモートセンシング学会編、理工図書、3,675円(税込)
- 「リモートセンシングのための合成開口レーダの基礎」大内和夫、東京電機大学出版局、4,515円(税込)
- "Digital Processing of Synthetic Aperture Radar", Ian G. Cumming and Frank H. Wong, Artech House, 137 USD
- 「地図を学ぶ−地図の読み方・作り方・考え方−」菊池俊夫・岩田修二編著、二宮書店、1,300円
- 「リモートセンシングの基礎【第2版】」W.G.Rees著 久世宏明ほか訳、森北出版株式会社、5,200円
- 「北海道農業のためのリモートセンシング実利用マニュアル」
- 「はじめてのリモートセンシング−地球観測衛星ASTERで見る」古今書院、4,000円
- 「宇宙から見る地球の姿 第16回「大学と科学」公開シンポジウム講演収録集」クバプロ、3,000円
- 「アースウォッチの旅入門」福田重雄著、誠文堂新光社、2,800円
- 「リモートセンシングデータ解析の基礎」長谷川均著、古今書院、3,500円
- 「図解リモートセンシング」日本リモートセンシング研究会編、(社)日本測量協会、3,500円
- 「リモートセンシング概論」土屋清編著、朝倉書店、5,665円
- 「熱赤外線リモートセンシングの技術と実際」日本写真測量学会編、鹿島出版会、4,500円
- 「人工衛星によるマイクロ波リモートセンシング」古濱洋治・岡本謙一・増子治信著、(社)電子情報通信学会、3,430円
- 「リモートセンシング工学の基礎」星仰著、森北出版株式会社、2,900円
- 「画像の処理と解析」日本リモートセンシング研究会編、共立出版、3,500円
- 「画像解析ハンドブック」高木幹雄・下田陽久監修、東京大学出版会、25,750円
- 「生物圏機能のリモートセンシング」、R.J.ホッブス、H.A.ムーニー編/大政謙次・恒川篤史・福原道一監訳、シュプリンガー・フェアクラーク東京、5,800円
- 「農業リモートセンシング」