
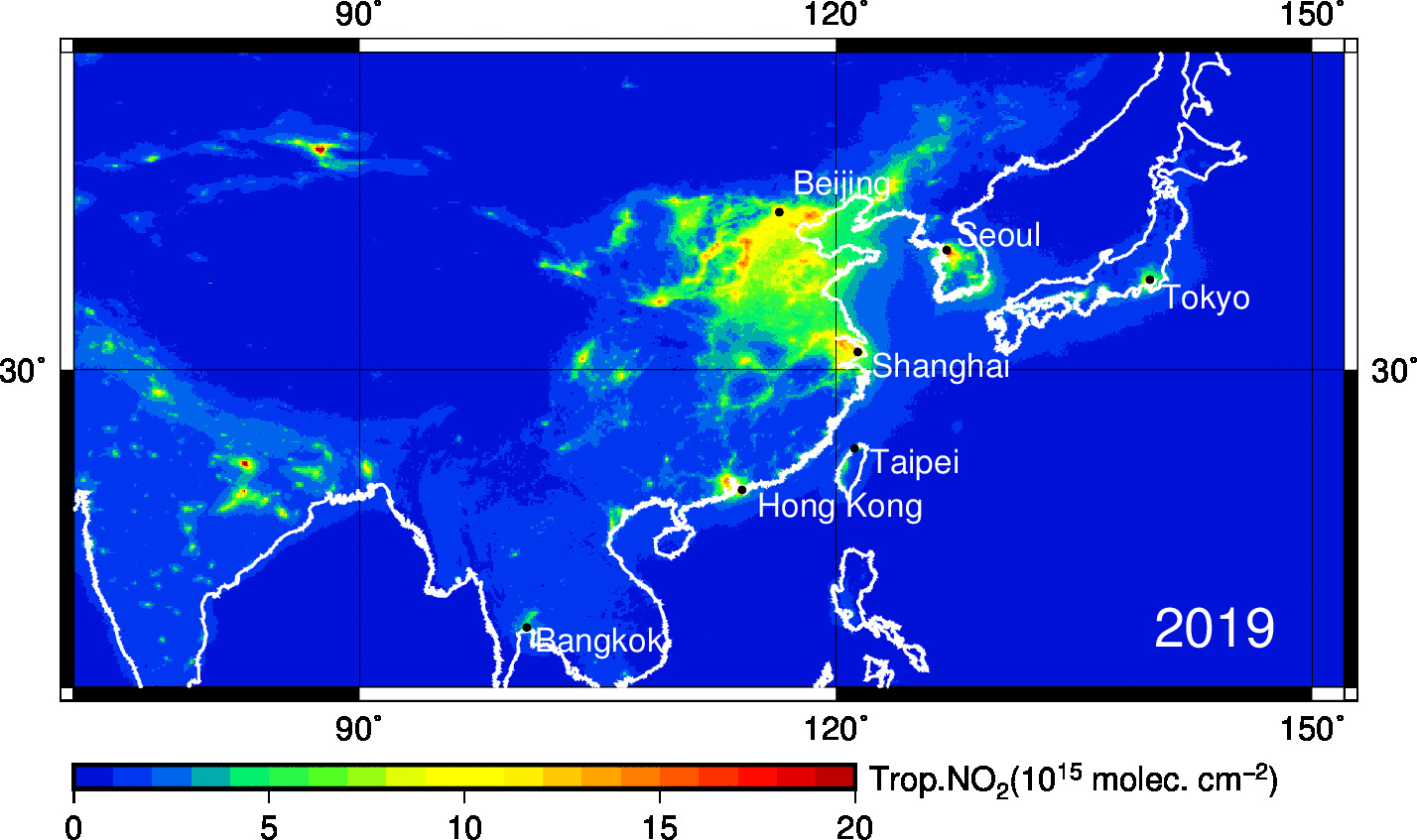
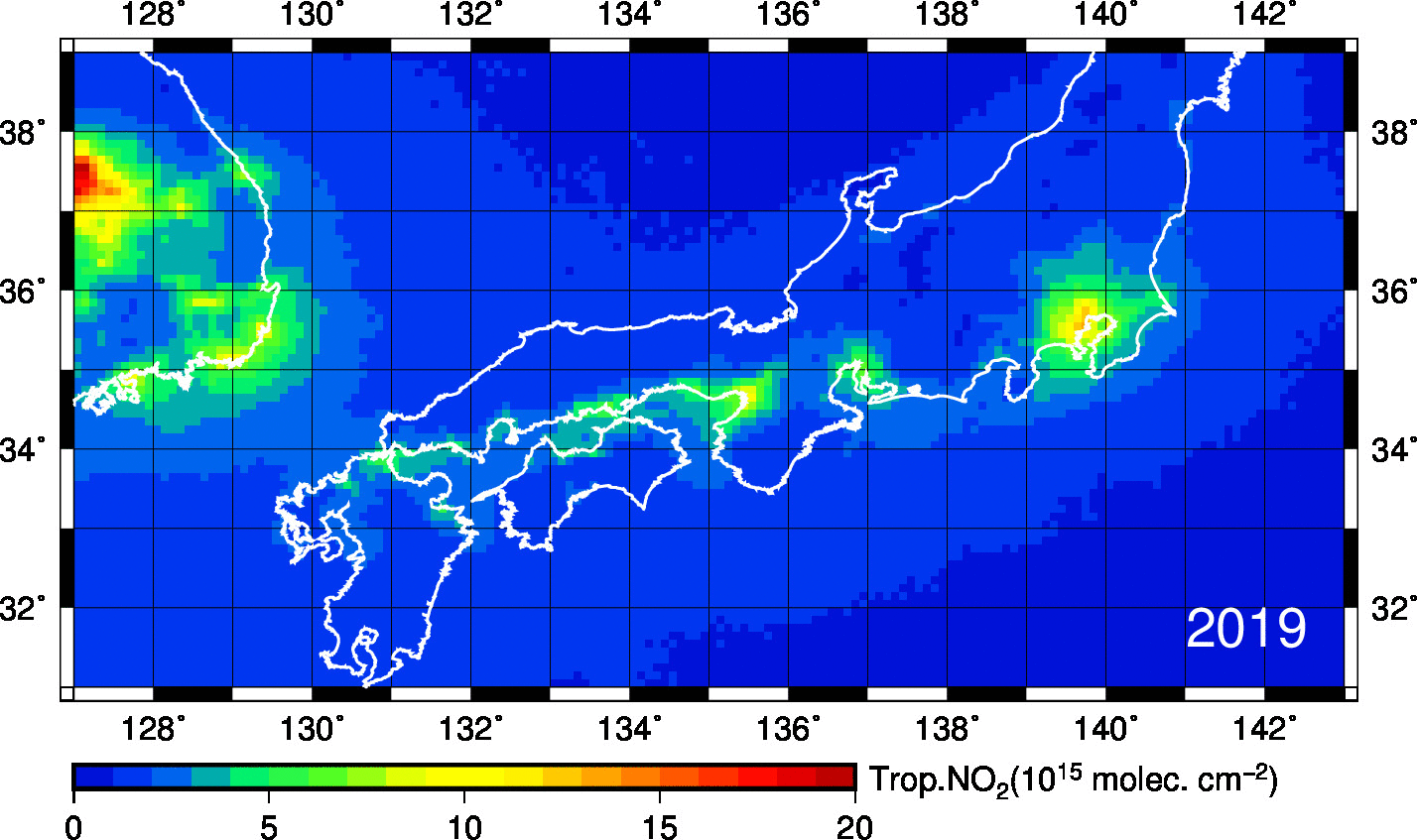
TROPOMI衛星センサによる対流圏NO2カラム濃度のマップ。年平均値のアニメーション。
■研究内容
当研究室の各メンバーの研究内容についてはこちらをご覧ください。
当研究室の各メンバーの研究内容についてはこちらをご覧ください。
■プロジェクト・関連コミュニティ (20220311時点)
科研費基盤B「低コストの受動型可視分光法による大気下層水蒸気観測技術の線状降水帯研究への新展開」
JSPS研究拠点事業「静止気象衛星観測網による超高時間分解能陸域環境変動モニタリング国際研究拠点」
千葉大学国際高等研究基幹研究支援プログラム「衛星ビッグデータとデータサイエンスの統合による地球環境・災害予測研究の新展開」
九州大学応用力学研究所共同利用研究「逆推計手法による東アジア域排出量データベースの高度化に向けた研究」
科研費基盤C「地上・衛星観測網による東アジアのエアロゾルの半世紀の変動とコロナ禍の影響の解明」
環境研究総合推進費「対策によるオゾン濃度低減効果の裏付けと標準的な将来予測手法の開発」
4大学連携事業「地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成(VL)」
国際地上リモートセンシング観測網(A-SKY)
環境研究総合推進費「国際観測網への発展を可能とするGOSAT-2の微小粒子状物質及び黒色炭素量推定データの評価手法の開発」(要パスワード)
国際地上リモートセンシング観測網(SKYNET)
NASA AERONET
気候変動観測衛星(GCOM-C)
雲エアロゾル放射ミッション(EarthCARE)
韓国の静止大気化学衛星観測計画(GEMS)
CCAC
CEOS
AGU
IGAC
日本地球惑星科学連合(JpGU)
日本大気化学会(JpSAC)
日本気象学会
科研費基盤B「低コストの受動型可視分光法による大気下層水蒸気観測技術の線状降水帯研究への新展開」
JSPS研究拠点事業「静止気象衛星観測網による超高時間分解能陸域環境変動モニタリング国際研究拠点」
千葉大学国際高等研究基幹研究支援プログラム「衛星ビッグデータとデータサイエンスの統合による地球環境・災害予測研究の新展開」
九州大学応用力学研究所共同利用研究「逆推計手法による東アジア域排出量データベースの高度化に向けた研究」
科研費基盤C「地上・衛星観測網による東アジアのエアロゾルの半世紀の変動とコロナ禍の影響の解明」
環境研究総合推進費「対策によるオゾン濃度低減効果の裏付けと標準的な将来予測手法の開発」
4大学連携事業「地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成(VL)」
国際地上リモートセンシング観測網(A-SKY)
環境研究総合推進費「国際観測網への発展を可能とするGOSAT-2の微小粒子状物質及び黒色炭素量推定データの評価手法の開発」(要パスワード)
国際地上リモートセンシング観測網(SKYNET)
NASA AERONET
気候変動観測衛星(GCOM-C)
雲エアロゾル放射ミッション(EarthCARE)
韓国の静止大気化学衛星観測計画(GEMS)
CCAC
CEOS
AGU
IGAC
日本地球惑星科学連合(JpGU)
日本大気化学会(JpSAC)
日本気象学会