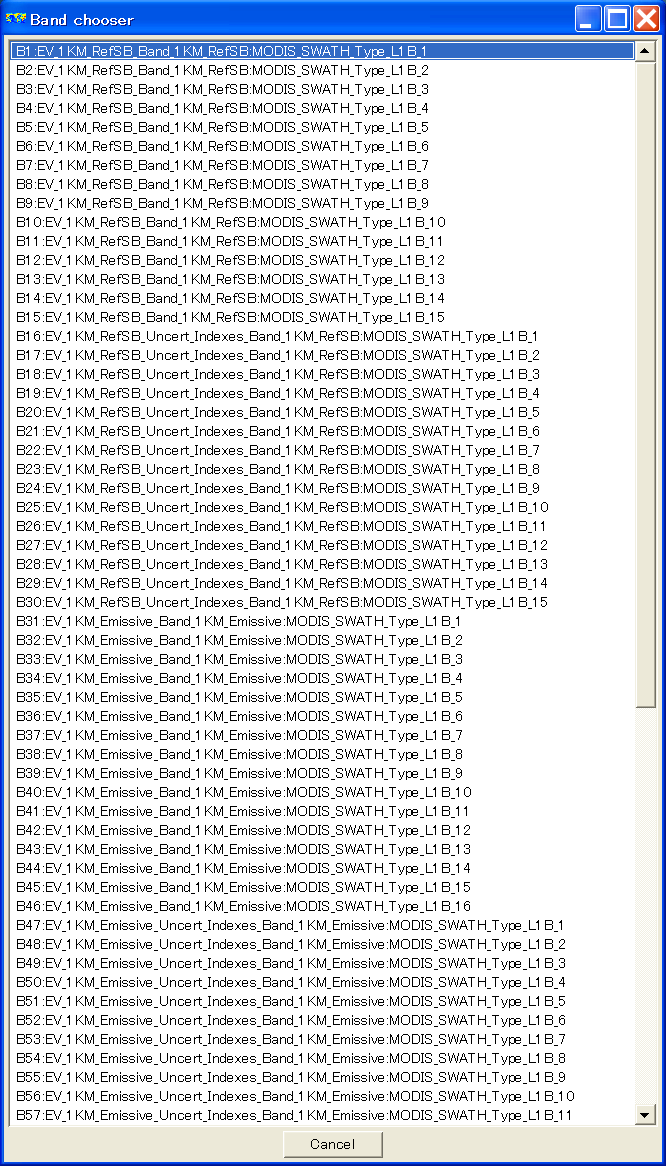
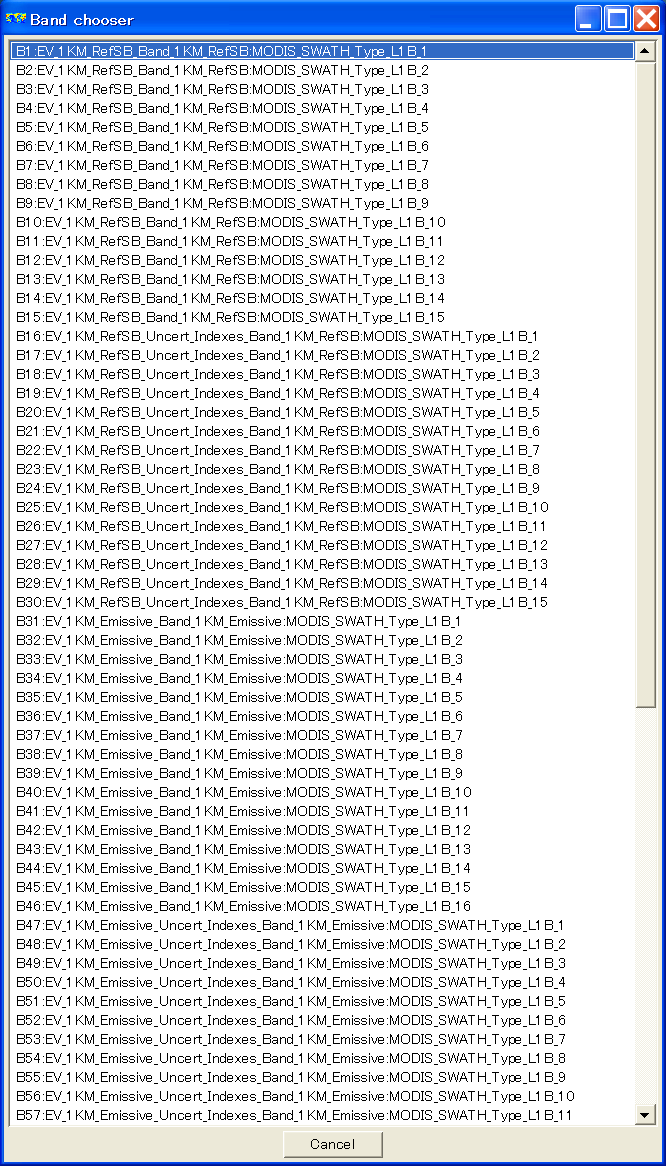
MODIS Lebel1Bデータの処理の実際
このページは完成しているわけではありませんが、持てる情報をなるべく早く出すため、リンク開始します。頻繁に更新する(かもしれない)ので時々覗いてみてください。
CEReSでアーカイブしているMODISデータは共同利用研究として様々な研究に利用できます。ここでは、画像処理ソフトウエアER Mapperと、MODISのHDF形式の様々な処理を行うHDF-EOSソフトウエアを使った処理の実際について紹介します。
ここでは、Windowsの使用を前提としていますが、Linuxによる処理は、ここを参照してください。
[使用するソフトウエアについて]
HDF-EOSはフィンランドのVTT社の製品で、MODISはじめいくつかの衛星データの画像抽出、放射量補正、幾何補正、等が可能です。詳細はここのマニュアルを参照してください。日本では㈱ビジョンテックが扱っています。
ER Mapperは汎用リモートセンシング画像解析ソフトウエアです。日本では㈱ビジョンテック、㈱CRCソリューションズで扱っています。
目次
1.ディレクトリ(フォルダ)の中身
アーカイブされているディスクのディレクトリから20050401を選択して中身を見てみましょう。
中には、こんなにたくさんのファイルが入っています。サンプルデータはここにあります。
これらのファイルの中で、MODおよびMYDで始まるファイルがMODISデータです。
2.画像の選択
一つのファイルを選んで画像を表示してみましょう。
MOD021KM.J20050401014538.20050401015726.hdf.gz
このファイルは名前から、以下のことがわかります。
| MOD02 | 画像データである。データプロダクトについては、ここを見てください。 |
| 1KM | 1kmの分解能のデータが入っている |
| J | JAXA受信の意味だと思います |
| 20050401014538 | 受信開始が、2005年4月1日の1時45分38秒という意味です。時間はGMTですのでJST(日本標準時)に直すには9時間を足してください。 |
| 20050401015726 | 受信終了時刻を表します。 |
| hdf | このデータの形式がHDFであることを表します。 |
| gz | ファイルはgzipで圧縮されているということです。 |
3.ファイルの解凍
gz形式の圧縮ファイルを解凍するには、プログラムgzipが必要です。http://www.gzip.org/からダウンロードできます。
あるいは、窓の杜等のサイトからgzipに対応する解凍ソフトをダウンロードして使うことができます。
gzipを使うとバッチ処理が可能になりますので、大量のデータを処理することができます。
ここでは、
gzip -d MOD021KM.J20050401014538.20050401015726.hdf.gz
としましょう。すると、
MOD021KM.J20050401014538.20050401015726.hdf
ができあがります。これがHDF形式の画像データです。
4.ER Mapperによる画像の表示
HDF形式をサポートする画像処理ソフトウエアとして、ER Mapperを使用して画像を表示してみましょう。ここでは、ただ表示させるだけです。
もちろん、ほかのアプリケーションも使用可能ですが、近藤研では最初にER Mapperを導入したので、ずっと使い続けています。
まず、HDFファイルを開いてみましょう。この中にはなんと92チャンネルのデータが含まれています。
(画像をクリックすると拡大します)
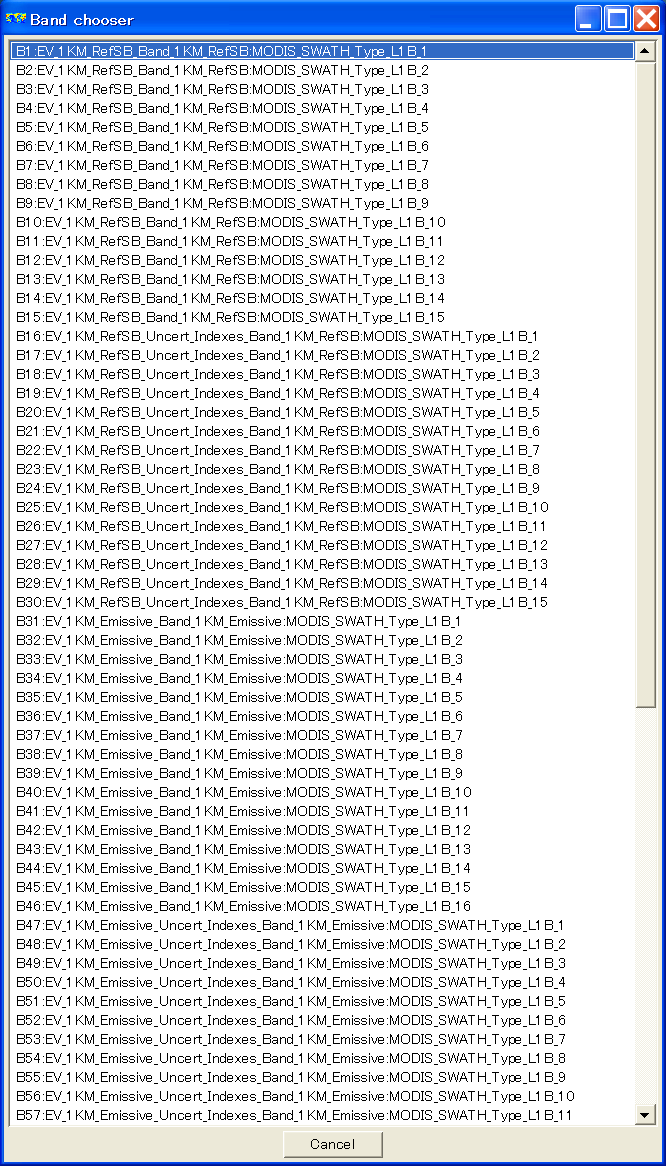 |
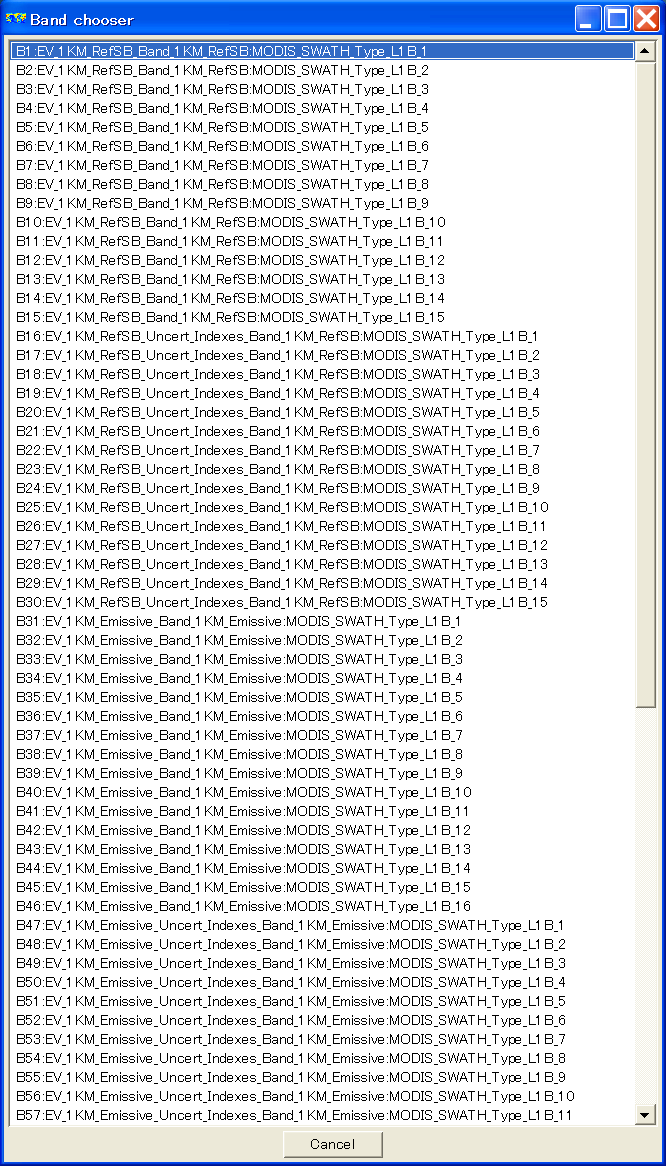 |
MODISセンサーのチャンネルは36ありますが、様々な情報が付加されています。ここにスペックに関するページがありますので参照してください。ER Mapperファイルのバンドと、MODISのバンドの関係はここを見てください。
1)プログラムスタート

HDF-EOSを起動したら最初に作業ディレクトリ(working directory)を設定します。
2)データのアンパックと ER Mapper による表示
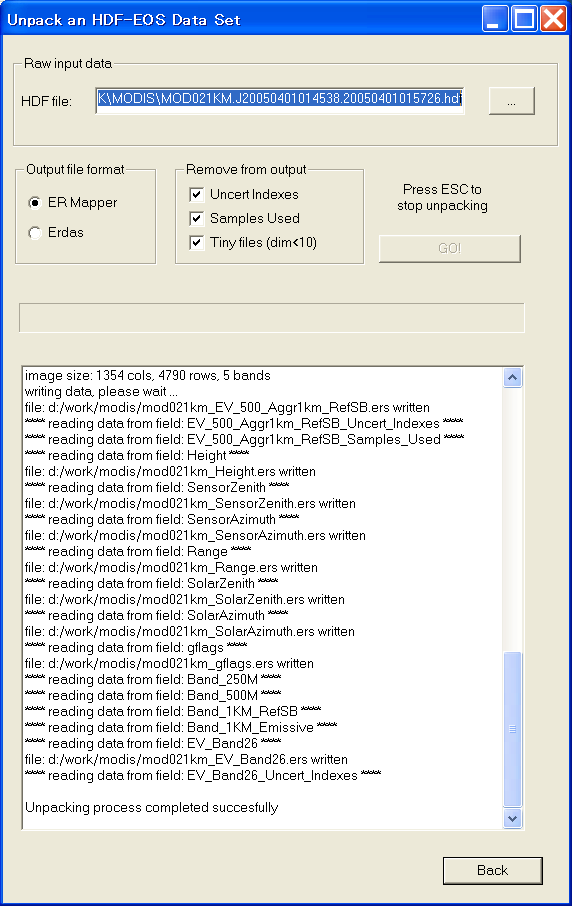
次に、Unpack HDF-EOSを選択しましょう。画面が現れたら、出力フォーマットを選択します。ER MapperとEardas形式がありますが、ここではER
Mapper形式を選択しておきます。
注)ER Mapper形式は、単なるBILファイルです。画像に関する情報は*.ersファイルに記述があります。
GOボタンを押すとファイルの展開が始まります。なお、ここで時刻が読み取れないとの警告が出ますが、JAXAのフォーマットが本家と若干異なるためです。ここでは、OKを押してそのまま処理を進めましょう。
できあがったファイルを下の表に示します。ここで、拡張子がないファイルがイメージファイルで、同名で拡張子がersのファイルがファイルディスクリプタです。これはER
Mapperの形式で、そのまま画像を取り込むことが出来ます。
hdfeos.log
mod021km_attr.txt
mod021km_Change in relative responses of thermal detectors
mod021km_Change in relative responses of thermal detectors.ers
mod021km_DC Restore Change for Reflective 1km Bands
mod021km_DC Restore Change for Reflective 1km Bands.ers
mod021km_DC Restore Change for Thermal Bands
mod021km_DC Restore Change for Thermal Bands.ers
mod021km_EV_1KM_Emissive
mod021km_EV_1KM_Emissive.ers
mod021km_EV_1KM_RefSB
mod021km_EV_1KM_RefSB.ers
mod021km_EV_250_Aggr1km_RefSB
mod021km_EV_250_Aggr1km_RefSB.ers
mod021km_EV_500_Aggr1km_RefSB
mod021km_EV_500_Aggr1km_RefSB.ers
mod021km_EV_Band26
mod021km_EV_Band26.ers
mod021km_gflags
mod021km_gflags.ers
mod021km_Height
mod021km_Height.ers
mod021km_Latitude
mod021km_Latitude.ers
mod021km_Longitude
mod021km_Longitude.ers
mod021km_Noise in Thermal Detectors
mod021km_Noise in Thermal Detectors.ers
mod021km_Range
mod021km_Range.ers
mod021km_SensorAzimuth
mod021km_SensorAzimuth.ers
mod021km_SensorZenith
mod021km_SensorZenith.ers
mod021km_SolarAzimuth
mod021km_SolarAzimuth.ers
mod021km_SolarZenith
mod021km_SolarZenith.ers
ER Mapperでmod021km_EV_1KM_RefSBを表示してみましょう。このファイルは15バンドを含みますが、、その情報は*.ers(テキストファイル)に書き込まれています。その観測波長域は本家のホームページを参照すると下記の様になります。ここで、Band 8~16がOcean Color/Phytoplankton/Biogeochemistry、Band 17,18,19がAtmospheric Water Vaporで、Band 26がCirrus Clouds Water Vaporの最初のバンドになります。バンド26が入っていることに注意。なお、hi、loはハイゲイン、ローゲインの意味だと思います。MODISのスペックはこちら。
| No. | Band | Bandwidth | Spectral Radiance | Required SNR |
| 1 | band 8 | 405-420 | 44.9 | 880 |
| 2 | band 9 | 438-448 | 41.9 | 838 |
| 3 | band 10 | 483-493 | 32.1 | 802 |
| 4 | band 11 | 526-536 | 27.9 | 754 |
| 5 | band 12 | 546-556 | 21.0 | 750 |
| 6 | band 13lo | 662-672 | 9.5 | 910 |
| 7 | band 13hi | 662-672 | 9.5 | 910 |
| 8 | band 14lo | 673-683 | 8.7 | 1087 |
| 9 | band 14hi | 673-683 | 8.7 | 1087 |
| 10 | band 15 | 743-753 | 10.2 | 586 |
| 11 | band 16 | 862-877 | 6.2 | 516 |
| 12 | band 17 | 890-920 | 10.0 | 167 |
| 13 | band 18 | 931-941 | 3.6 | 57 |
| 14 | band 19 | 915-965 | 15.0 | 250 |
| 15 | band 26 | 1.360-1.390 | 6.00 | 150(SNR) |
その他のファイルについても、同様の操作で画像化は簡単にできます。対応表はこちら。
画像を表示してみました。さて、これでとにかく画像化はできたわけです。
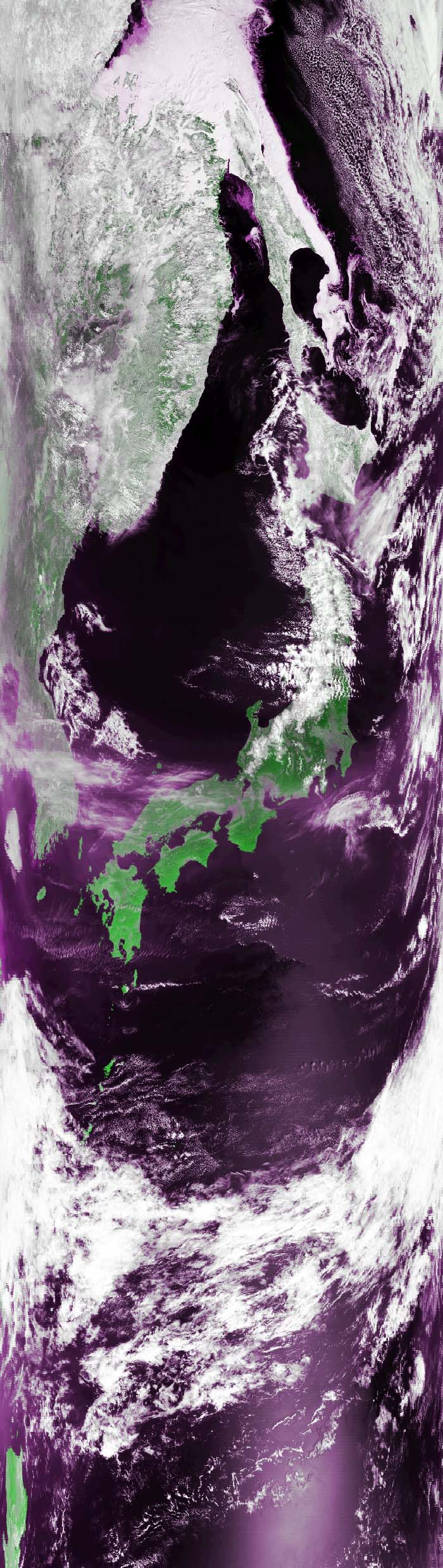 |
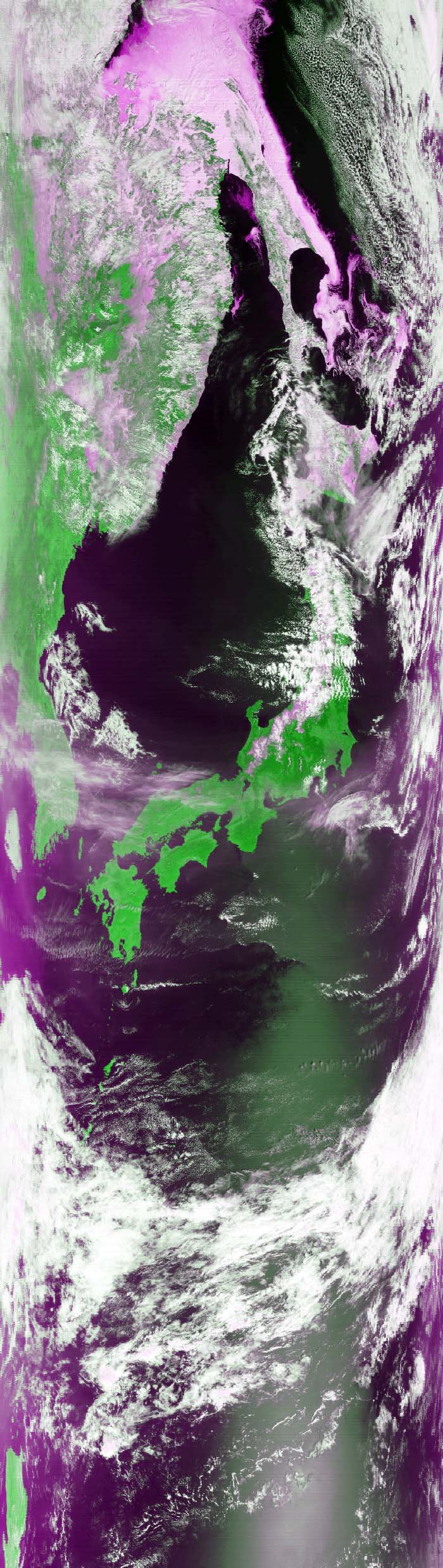 |
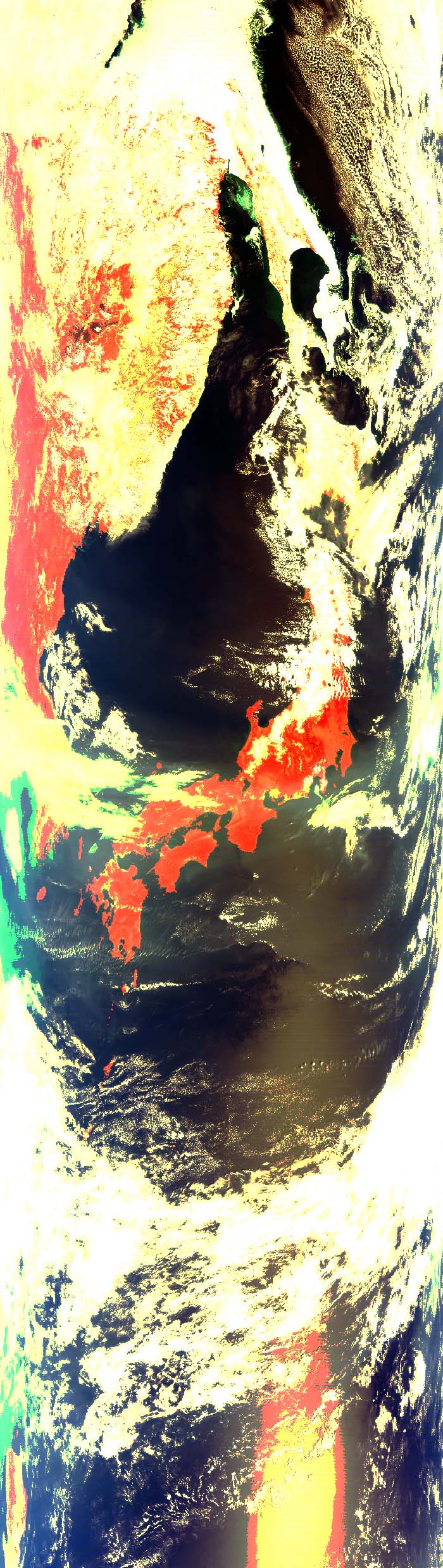 |
| 250m BGR=1,2,1 | 500m BGR=3,5,3 | 1km BGR=8,12,16 |
3)放射量補正
MODISの短波のバンドに対しては、"MODIS Reflective band calibration"のメニューが用意されています。入力データとしては、
が必要です。ここで、Image Fileはファイル名にRefSBが含まれているファイルを指定します。次に、1km分解能のセンサーと太陽の角度に関するファイルが必要ですが、そのファイルはMOD3に含まれています。MOD2に含まれているファイルは分解能が粗い(~10km)ので使えません。
そこで、ここから現在解析しているファイルに対応するMOD3ファイルをダウンロードし、3.ファイルの解凍と同じ手順でファイルを取り出しましょう。
MOD021KM.J20050401014538.20050401015726.hdf
これが解析中のファイルですので、対応するMOD3ファイルは
MOD03.J20050401014538.20050401015726.hdf
これになります。
解凍が終わると、こんなにファイルが生成されます。これらのファイルを使って放射量補正を行うと...
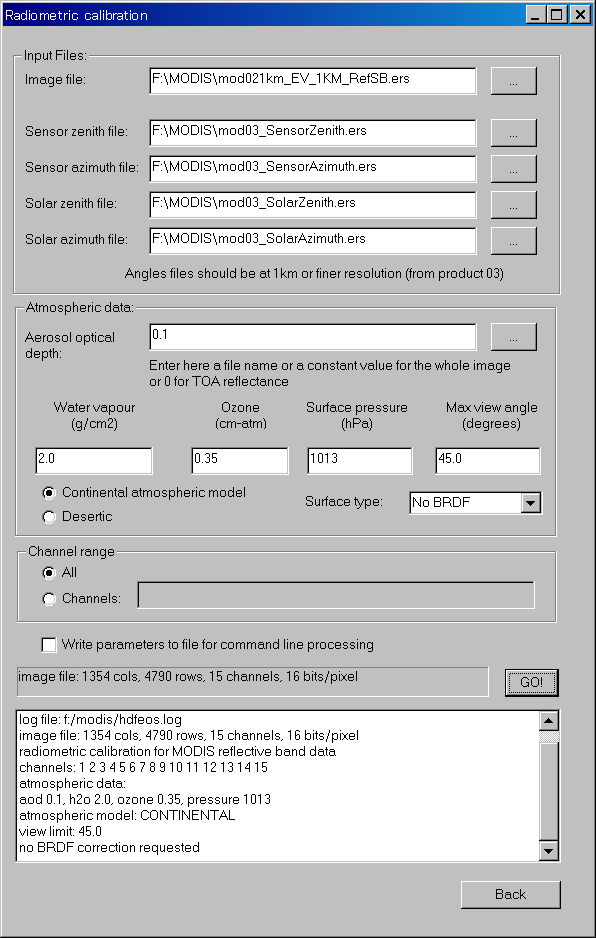
どうもうまくいきません。もうちょっと勉強してみますので、暫しお待ちください。
4)輝度温度補正
MODISの熱赤外バンド(バンド20~36)を輝度温度(ケルビン)に変換することができます。その計算方法は、ここのマニュアルを参照してください。
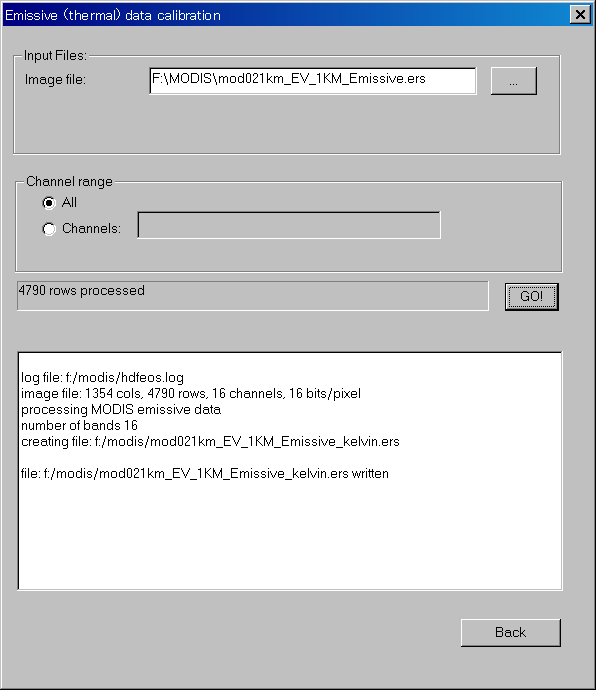
使い方は簡単で、ファイル名を入力するだけです。ファイルは名称にEmissiveが含まれているものになります。チャンネルを指定(すべても可能)して、GOボタンを押すと処理が開始されます。出力ファイルはもとの名前に_kelvinが吹かされたものになります。
HDF-EOSではGeodetic(Plate Carre)すなわち、等緯度経度グリッドとメルカトル図法を選択することができます。データムはWGS84です。
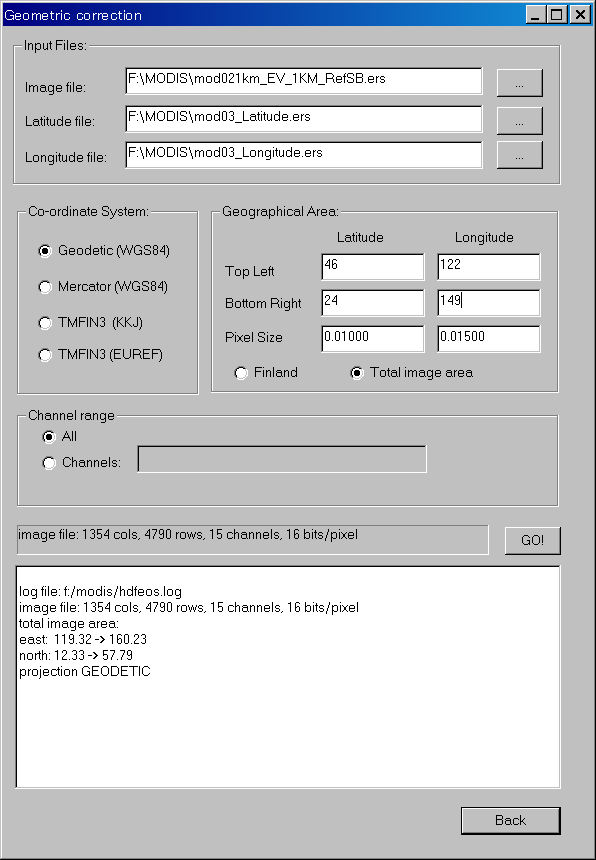
Image Fileと緯度経度ファイルを入力します。緯度経度情報はMOD3で作成されたファイルを使用してください。
ここでは、画像出力範囲として緯度が北緯24度~46度、経度が東経122度~149度を指定しました。分解能は東西0.01度、南北0.015度を指定してあります(もちろん、可変です)。GOボタンを押すと処理が開始されます。
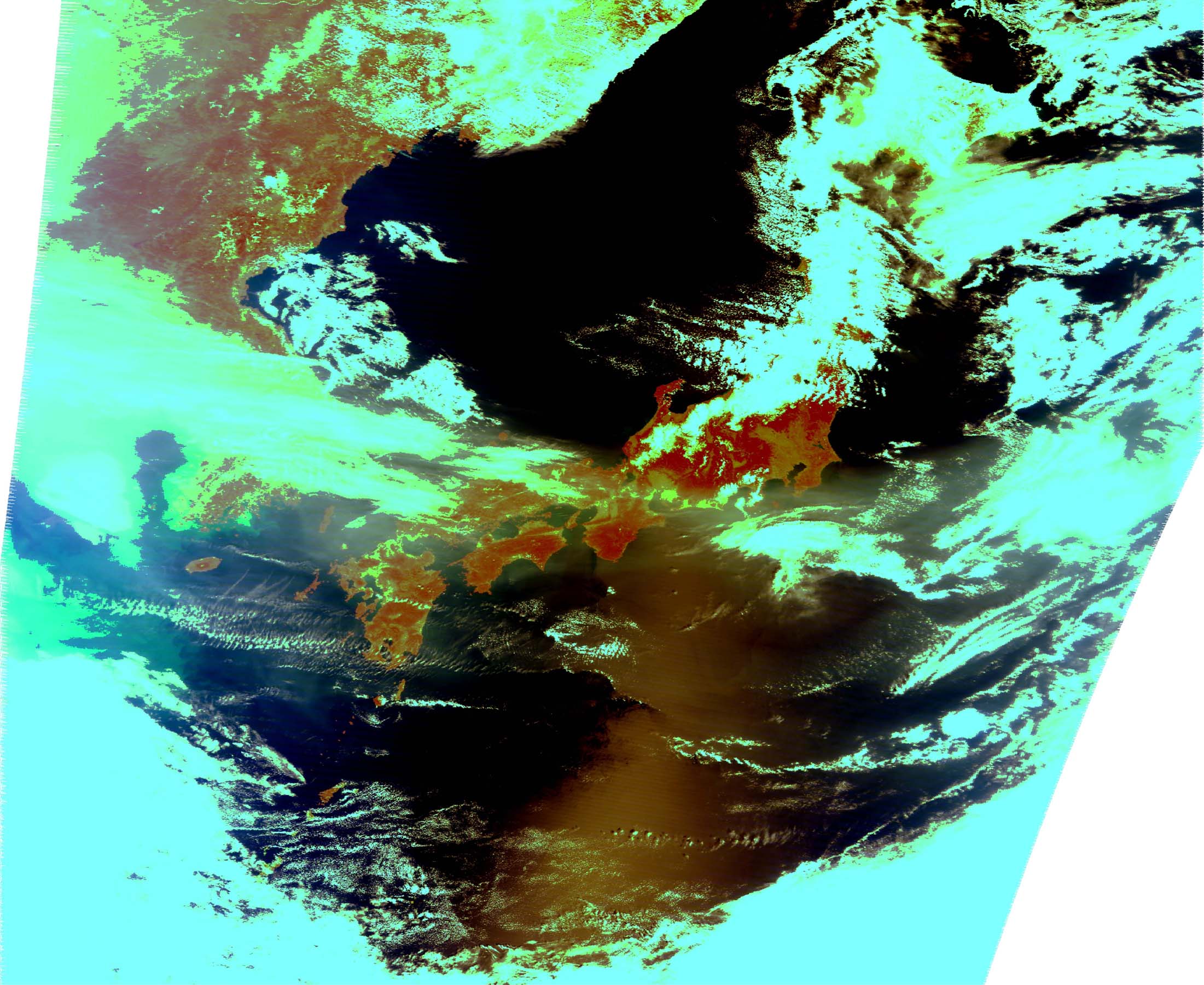
画像はすぐに出来上がります。元のファイル名に_rectが付加された名前でセーブされ、この例では画像サイズは2201ピクセル×1801ラインになります。ということは、メッシュではなく、グリッドにおける値として出力されていることがわかります。
HDF-EOSではMODISセンサーで見られるBOWTIEを補正できます。ここのマニュアルの表紙にその効果が示されています。
さて、ここまでできたらMODISを使っていろいろ遊ぶことができますね。
以上の処理はHDF-EOSを使って対話的に行うことができました。しかし、これでは大量のデータを扱うには少々不便です。そこで、HDF-EOSにはコマンドライン版(HDFEOS_COM.EXE)も準備されています。バッチファイルを作成することにより、大量のデータ処理が可能になります。
i)HDFファイルの解凍
コマンドプロンプトから以下のプログラムを起動します。HDFEOS_COMは同じディレクトリに置くか、Pathを設定しておいてください。
HDFEOS_COM task uphe df MOD021KM.J20050401014538.20050401015726.hdf
HDFEOS_COM task uphe df MOD03.J20050401014538.20050401015726.hdf
taskの後に続くキーワードで処理を指定します。ここで、upheはHDF-EOSファイルの解凍(unpack)を指示します。dfの後には処理するファイル名を記載します。
ii)幾何補正
幾何補正のtaskはgeoで、parfの次に以下のようなパラメータファイルを指定します。
HDFEOS_COM task geo parf filename
[パラメータファイルの内容]
imf: f:\modis\work\MOD021KM_EV_1KM_RefSB.ers
lat: f:\modis\work\MOD03_Latitude.ers
lon: f:\modis\work\MOD03_Longitude.ers
crd: geodetic_wgs84
area: 122 149 0.01 24 46 0.01
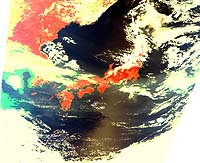
入力ファイルと緯度・経度ファイル(MOD3)を指定し、座標系が等緯度・経度(Geodetic、Plate Carre)、データムがWGS84であることを指定します。areaは経度範囲と増分、緯度範囲と増分の6つの数字を指定します。このパラメータファイルは分解能0.01度の日本を含む範囲の画像データを出力します。
さて、これでMODIS L1Bの一通りの処理がバッチでできることがわかりました。大量のデータを処理するスクリプト(バッチファイル)については、もう少し考えてみようと思います。近日中に、特定領域のサブセットの作成に取り掛かりたいと思います。
お問い合わせはこちらまで![]()